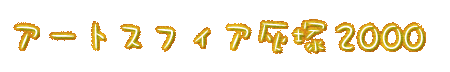アリストテレスが『詩学』で言うには、物語には「始め」と「中間」と「終わり」がある。この言明はトリヴィアルに見えるが、「始め」「中間」「終わり」という語がそれぞれ単に記述的な意味だけでなく、規範的な意味で用いることもできるために事態は複雑化する。だからこそ「この作品の終結部はちゃんと終わっていない」といった批評が可能になるのであり、小説のモダニズムではこの規範を崩す試みが数多くなされるに至った(だが同時に近代批評は、「古典的」小説が「常にすでに」規範を打ち立てると同時に崩してもいたということを「発見する」)。なぜなら物語の進行に関する規範はとりわけ「始め」と「終わり」において顕著にコード化されていたからである。
だがこのように考えると、ゲームにおいて局面が最も複雑化するのが中盤であることが判明する。プレイヤーが取りうる「手」の選択肢の数が最も増大する中盤において、分岐点は至る所にあり、局面の進行を見極めることが最も困難になる。しばしば自動的に進行する序盤や終盤とは異なり、プレイヤーの裁量が最も問われるのが中盤であることは疑いない。もっとも、正確に言うなら、「序盤から中盤への移行」と「中盤から終盤への移行」という二つの移行こそがゲームにおけるクリティカルモメントである。プレイの始めと終わりを「定石」によってフレーミングすることで、熟練者は「どこで定石が終わるのか」(序盤)、あるいは「どこで定石が導入されるのか」(終盤)という特異点のありかを探り、中盤への、あるいは中盤からの移行を首尾良く成し遂げようとする。
もちろん、物語の進行の一例としてゲームを援用することが、常に可能とは限らない。安易な芸術比較論、例えば「絵画は詩のごとく」といった諸芸術の照応理論は過度の一般化のために妥当性を欠くことになりがちである。たとえモダニズムにおけるメディウムの純化というプログラムが疑問に付されようとも、各々のジャンルがそれぞれスペシフィックな特性を持つ、という主張の強力さを疑うことは困難であろう。すると上述のゲームに関する考察を、そのまま物語に適用することには慎重にならなければならないのではないだろうか。しかし芸術比較論で実際に問われていたのが単なるイメージやテーマの類似ではなく、構造的な相同性であることに注意を払う必要がある。言い換えると、問題になるのは「項Aと項Bの類似」ではなく、むしろ「関係Aと関係Bの対応」である。こうして改訂された比較論を推し進めてみると、物語では「プレイヤー」の位置が問われていることが直ちに判明する。そもそも定義上プレイヤーを必要とするゲームとは異なり、「物語のプレイヤー」という表現は明確さを欠いている。結果として、ゲームと物語の関係の非対称性が「プレイヤー」に集約されることが明らかになる。芸術比較論は、このようにして構造的相同性と同時に、非─相同性の所在の発見術として用いることもできるだろう。
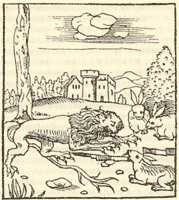
「物語のプレイヤー」については後述することにして、ゲームで言うところの中盤、すなわち物語の「中間」部分について考察を続けよう。物語におけるナラティヴの進行を統御しようとする様々な試みはレトリックと呼ばれる。レトリックは「それはメタファーにすぎない」というように、対象を貶める手段としてしばしば用いられる。しかしレトリックは物語において、認知的機能を担い、出来事の因果性を操作する役割を担っている。ナラティヴの進行が取りうる複数の可能性の束を、様々な形で選択して縮約すること。レトリックのこのような機能は、ゲームの中盤におけるプレイヤーの状況と対応しているかのようである。だが、レトリックはいわば「中盤における定石」とでも言うべきものを構成することによって、プレイヤーの役割を代行し、免除する。そしてこのことはとりわけ格言において見ることができる。
架空の二つの言明、「愚か者が穴に落ちる」「愚か者が崖を飛び越える」。このいずれもが格言となりうる。その際、前者は賢さの必要性を、後者は愚かさの有用性を示すものになるだろう。ここで両者を分岐させているのは、「愚か者」の行為の帰結である。けれどもこれらの言明それ自体はある出来事を記述しているだけなのであるから、なんら「教訓」を含まないものとみなすこともできよう。それを妨げているのはもちろん「愚かさ」という評価語の導入である。評価は行為の帰結に基づいて事後的になされる(穴に落ちた者が「愚か」とされる)ものであるにも関わらず、これらの言明では予め「愚かさ」が行為者に指定されてしまっている。格言が与える奇妙に無時間的な印象は、評価の先取りによって得られる事前性が、行為の連鎖を空間化していることに起因する。図版と題辞のカップリングによって成立するアレゴリーやエンブレムは、「絵画は詩のごとく」の範例とされたが、それは題辞が教訓機能を遂行すべく予め空間的なエクフラシスと化し、他方で図版が例示機能を遂行すべく予め行為のディエジェーシスと化すことによって、両者の対応が成立していたからに他ならない。
マルセル・モースは、返礼を要求しないはずの贈与が実際には交換機能を担うことを示した(『贈与論』)。格言が与える教訓も含め、数多くの儀式はこのような「贈与による交換」をコード化している。「純粋贈与」は贈与者の力を示すことになり、間接的に「不純化」する。呪術が試みる「呪い」でさえ、同時に「呪い返し」といった反対進行の可能性を有しているのだ。こうして儀式においては、たとえ「幸運」や「不運」が一方的に贈られてくるように見えようとも「反転」の余地がある、とされるに至る。そして出来事の反対進行が生じる「逆転」の瞬間は、同時に無知から知への移行という「認知」の瞬間でもありうる。アリストテレスが、『オイディプス王』における「逆転」が「認知」と共に起こると述べるとき、そこで問われているのもやはり、ナラティヴ進行の「贈与による交換」であるとみなすことができる。物語と儀式は共に、逆転と認知の瞬間を形象化することで、諸々の出来事を「贈与による交換」という形で循環させているのである。
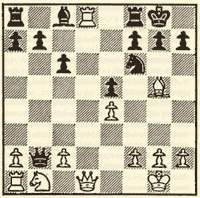
反対進行の可能性が最も想定しがたいもの、それは時間であろう。しかし、教訓のレトリックが「物語のプレイヤー」を代行するという前述した事態は儀式にも当てはまる。時間さえもが反対進行の対象となりうるのだ(奇跡)。だが時間を反転させる試みは、レトリックの統御を超えていると言わざるを得ない。なぜならナラティヴ進行の統御可能性それ自体が、時間の「贈与」によって成立しているからである。仮に時間という「純粋贈与」を交換可能にする試みがなされるにしても、そこでもなお、過去、現在、未来という時間の三次元がフレームとして用いられており、このフレームを一種の「純粋時間」とみなすことができる。前述したように、格言は評価を先取りすることによって行為の連鎖を予め空間化するが、それは儀式と同様、時間が「取り返しの付かないもの」として与えられることを条件としている。格言や儀式において、行為者たちは局面の進行を様々なやり方で統御しようとするが、そのつどの局面を恣意的に設定するわけではない。ここで局面は、一種の「純粋空間」としてそのつど与えられているのだ。端的に言うなら、反対進行が想定不可能な形で与えられるもの、それは時空間である。純粋時間と純粋空間が最も良く定義されているのはゲームにおいてである。例えばチェスにおいて、純粋時間はプレイヤーの「順番」、純粋空間はチェス盤で繰り広げられる「局面」として現れる。それは儀式や物語にとっても不可欠な成立条件なのである。
したがって「物語のプレイヤー」を「物語内の登場人物」から区別する必要があるだろう。『オイディプス王』における「逆転」と「認知」の瞬間において、自己の運命に打ちのめされるのは、もちろん主人公のオイディプスである。しかし運命の反転は読者に前もって提示されている。ナラティヴ進行に真に立ち会うことになるのは読者なのだ。だが厳密には読者が進行を統御するわけではない。他方、贈与の審級に位置している時間や局面(純粋時間と純粋空間)は、物語におけるプレイを可能にする条件であり、プレイヤーではない。むしろプレイヤーは、物語によってそのつど構造的に要請される次元に位置している。まず第一に、純粋時間や純粋空間が物語を与えるのだが、今度は物語がプレイヤーを与えることになる。「物語のプレイヤー」とはこの二重の贈与によって定義される存在者であり、読者、登場人物、さらには作者といった、物語に関与する様々な人称性の次元のそれぞれの位置を占めつつも、それらからは区別されるのである。
こうして「プレイヤー」をめぐるゲームと物語の関係の非対称性が再定義されるに至る。「物語のプレイヤー」は、「始め」と「中間」と「終わり」のそれぞれの進行形式に応じて、逆転や認知のプロセスを用いつつ、物語の局面のそれぞれにおいて、様々な出来事を出現させる。こうした出来事は、ときには純粋時間や純粋空間の条件付けに対してすら作用するだろう。エンブレムや儀式もこうした出来事形式の一つに他ならず、ここから「絵画は詩のごとく」という問題を単なる芸術比較論の問いを超えた、より一般的な仕方で思考することが可能になる。 |