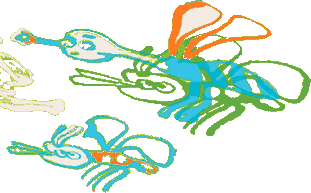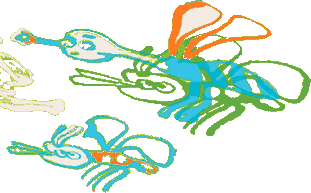|
 |
 |
 |
| ■□ トーク内容 |
 |
まず、昨年この旧顕徳寺の改修ワークショップを行った建築史家の中谷礼仁さんより、実際に改修に携わってみると、作り変えた方が良い部分と、残しておいたほうがよいものが出てくる。制作することで残す物は何かという規準が自ずとできてくると話されました。
それに引き続き、木田元さんは構築物ができるときに改めて「自然」という見方が発見されると指摘され、新しくできるものとの関係において「自然」が現れると述べられました。
また、子安宣邦さんは大阪の懐徳堂(江戸時代の朱子学の学校)について触れ、商人が自ら学ぶために学者を呼び開校したという話しを例に、学ぶことに現在を過去と未来とにつなげていく鍵があるのではないかと説かれました。
最後に灰塚アースワークプロジェクトに長く関わっている岡崎乾二郎さんが、この地域で行っている設計やデザインも、その都度「いま・ここ」にある物の変更の可能性を考慮し、過去から学びつつ制作を行っていくことでその都度解決策をだしていく、とまとめました。 |
|
 |

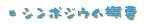

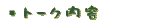

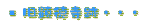

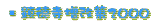 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| ■□ ハイデガーの自然観と芸術観 |
 |
こんにちの私たちにとって「自然」とは「空や大地、動物や植物」、あるいは「人間のつくり出せないもの」を指す概念ではないでしょうか。これらは自然に関する考え方の二つの伝統的な哲学と合致しています。
自然(ピュシズ)に対する考え方(哲学)はプラトンの教説と、アリストテレスの教説が引き継がれた伝統に分かれます。
プラトン学派において自然は「空や大地、動物や植物」を指す概念です。人間と動物(自然)を素材によって区別出来ないと考えたプラトンは、慣習(エートス)や制度(ノモス)の有無によってそれらを区別します、慣習などに規定されない存在物を自然と見なしました。一方、アリストテレスは物の構成のされ方を重視し人間の造り出せるもの、つまり<技術によって存在するもの>以外のものを<自然によって存在するもの>と考えました。
木田元さんが永年研究を続けてきたドイツの哲学者、マルティン・ハイデガー(1889〜1976)は上記のように哲学の伝統を整理し、自然が消極的に規定されてしまう考え方や、自然が存在するもの全体の中のある特定の領域(部分)を指す考え方、つまりプラトンやアリストテレスを含む、<ソクラテス以降の哲学者>の哲学、形而上学(物の存在する原因を見つけようという考え方)を強く批判しています。
彼によれば、本来自然とは<nature of spirit(精神の本性)>という時の使われ方が正しい。
ソクラテス以前の思想家は自然を物体的、部分的なものと捉えずあらゆる存在が生ずる「原理」と考えていました。「自然」は物の<本性>や<真の在り方>、<自ずからなること>を意味し、これはラテン語<ナテューラ>やギリシア語<ピュシス>にもあてはまる。そして自然の部分的なとらえ方は思考の堕落であると主張します。
形而上学(メタ・ピュシス)はものが存在する原因に遡ろうとする哲学であり、「存在者が何であるか」という<問題>と「存在者が存在する」という<事実>を区別するけれど、偉大な思索者であるギリシア人は「存在者が存在のうちに集められていること、存在の輝きのうちに存在者が現われ出ているということに驚」くのだと言います。
その主張によれば、古代ギリシア人にとって<制作(ポイエーシス)>は近代的な物の製造の意味ではありません。<制作>は無限定な混沌から世界という場へ存在者が現われてくる驚くべき出来事であり、人間による自然の破壊でなく、元来自然の運動(キネシス)の一バリエーションである、と。
晩年の著作『芸術作品の起源』においてハイデガーは、人間と自然の関係を論じ、<人間の制作>とは自然から真理(イデア)を取り出すものでなく、物事が生じること、その本性の発現を助けることであると定義しています。「暗い森の中に明るみが開かれて初めてその光のもとで全ての物が形を現すことになるが、同時に森の暗さもそれとして見えてくる」と書き、人間が森を開き明りを持ち込む事(制作)を、森(自然)の中に発見される明るみと人間の住まう世界を囲う暗がり(大地)のせめぎあいの発生とみなします。ハイデガーは芸術作品の制作に一つの世界を開く存在論的機能を認め、制作を通じて自然も人間の住処も生じると考えました。
木田さんは顕徳寺でこうしたハイデガーの自然観、芸術、制作観について話し、自然への破壊的な人間の介入に警戒しながらも人間と自然の良き関わり方を探ることの大切さを述べておられました。
(文責:坂中俊文) |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
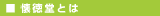 |
 |
| ■□ 懐徳堂とは |
 |
<朱子学>は、孔子の遺した経書と呼ばれる『論語』などの儒学書を解釈(注釈)する学問であり、荀子、墨子などなどにより、人間のありかたを教える道徳として体系化されてきました。江戸期の日本においても信仰や慣習とは違ったかたちで学問化され教えられます。
18世紀中後期、伊藤仁斎、荻生徂徠という巨大な朱子学者の去った後、松平定信の寛政の改革にあたり「朱子学」の再興を目指し推進したのが、懐徳堂の中井竹山(1730〜1804)に近い人間を中心としたグループでした。
大坂に生まれた懐徳堂は近世江戸の朱子学の要をなす学問所であり、中井竹山や弟、履軒、他に富永仲基などの偉大な学者を生みます。初代学主は三宅石庵(1665〜1730)。知識の私有化、秘境化を避け、権威主義を廃するため、学主の地位は決して世襲せず私物化しないというのが重要な運営規則でした。
朱子による経書の注釈とは、経書理解のあり方を通じ「世界とは何か」や「人間とは何か」という形而上学的な問題に答える作業であり、この哲学的立場が14世紀以降中国、朝鮮、日本を思想的に支配します。仁斎や徂徠の行った批判的な解釈も、先立つ注釈を前提としながら『論語』の正しい意味を読み出す事を目的としていました。懐徳堂は、この朱子学の正統の伝統に批判的な目を向ける学者によって担われます。たとえば四代目懐徳堂学主中井履軒(1732〜1817)は『論語逢原』のなかで、朱子の形而上学的な思惟(考え方)は『論語』理解に不適切であると述べ、経書解釈の学としての経学の<解釈のあり方>を問題化しました。
履軒の学問は『論語』を解釈するという行為をメタレベルで検討するものであり、朱子が解釈行為を通じて正しい意味や正統的な儒学を再生産した過程を解明し批判します。大きな理念の展開と離れた場所で、批判的な視線を共有する知識人を「懐徳堂」は成立させました。
懐徳堂の運営は元学生であった者が後に学問上、経営上で支えることによって成り立っていました。財政的には五同志と呼ばれた大阪の有力な商家を中心に、身分的に不安定な中間層(商人達)が支えました。彼ら商人達もまた市井の知識人として懐徳堂に学び、町人が広く世界の現状を認識できる場として、多くの知識人と文化を輩出しました。
現代の日本思想史を代表する研究者、子安宣邦氏によれば、時代に対する批判的な知
識を共有し、吟味された知識を人々に変わって世に提示する事を己の内的な責務とす
る新しいタイプの知識人は、18世紀中後期の大坂懐徳堂の周辺に始めて成立します。
知的交流の中心としての大坂が、こうしたコモンピープル、コモンセンスの成立を支えた懐徳堂の思想の基盤にあります。
子安さんは顕徳寺という場所で、懐徳堂の学校の在り方に、様々なものを生む可能性を見い出そうとされていました。学校とそれを支える人々の関わり方が文化を生む可能性です。
まったく考え付かなかった規則や自由を吟味し生み出す場としての学校は、こんにちの私たちにとってもまだまだ魅力があるものではないか、と述べておられました。
(文責:坂中俊文) |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |